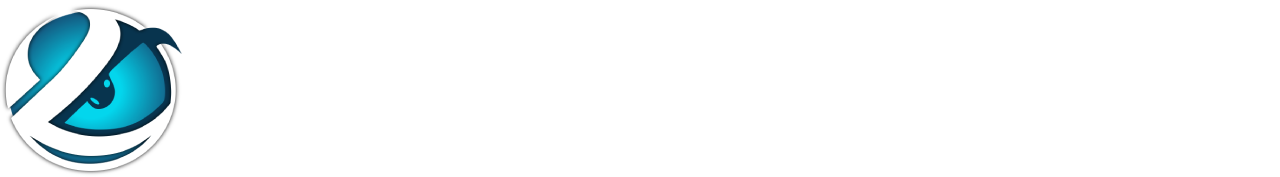思わずギャンブルがしたくなるサウンド

ギャンブルゲームを促すには「音楽」が効果的?
音楽が人々の気分、行動、知覚に及ぼす影響については、長年にわたって広く研究されています。そして複数の研究により、その関連性が立証されています。その結果、様々な状況下において、人の感情に影響を与えるよう、音楽が意図的に選択されるようになっています。
たとえば店頭で流れる音楽は、商品を選ぶ時間や購入金額に影響を及ぼします。また、行列に並ぶ時間への印象をよくするために、音楽が利用されることもあります。そしてもちろんカジノでも、音楽は心理戦略の一環としてよく利用されます。
カジノでは、ベッティングのスピードは、音楽のテンポに影響されます。ハイテンポの音楽を聴くことで、ベッティングのスピードが上がることは研究により実証されています。また、賭け金の総額や1回あたりの掛け金の大きさにも、音楽が影響することを立証した研究もあります。ここで、BGMによってベッティングスピードを上げさせる方法について興味深い見解があるので、早速見てみましょう。
BGMは、スピード感のあるノリのいい曲から、ゆったりとしたテンポの曲まで、ゲストが長時間プレイしたくなる環境や雰囲気を作り出すために利用されています。音楽が行動に与えるさまざまな影響の研究や、音楽がギャンブル行動に与える影響の研究などが行われ、興味深い結果が得られているのです。
カジノのような場所では、特に「長く滞在したくなるような音楽」がかけられていることをご存じですか?つまり、カジノとは、物事をよく理解している賢い人たちが設計した、非常によく作られた施設なのです。そこで、カジノが採用している音楽について、さまざまな角度から説明したいと思います。
特に「なんだかカジノに操られているんじゃないかな?…」と疑問に思ったことがある方はいますか?その疑問はもっともです。そしてその答えもまた明白です。つまりカジノは本当に、ゲストが長居したくなるような音楽を流して、ゲストの感情や行動を操作しているのです。
ただし、このようにカジノのやっている行為は違法ではありませんが、ギャンブル好きなお金持ちで、ちょっと軽率な人にとっては、リスキーかもしれませんね。いくら音楽でノリに乗っていても、ギャンブルゲームに興味がなければ立ち去るだけですが、ギャンブル好きな人に限っては、カジノ音楽の罠にはまってしまいます。
いんたーかじのはオンラインで完結するので、雰囲気にのまれることはないでしょう。
カジノ店舗は、ゴージャスながらも狡猾な企業であり、ゲストを刺激するためなら、あらゆる手段を用います。ゲストを惹きつけるため、カジノフロアにも莫大な費用と時間をかけています。長時間フロアにいると、ほぼ間違いなく、知らず知らずのうちにギャンブルを続けてしまうことでしょう。
ちなみに、カジノの選曲は、割にシンプルです。というのも、世界で人気トップの音楽を選べばいいからです。たとえば、自分の好きな曲がカジノでかかったら嬉しくなりますよね?カジノの設計者はこのようにして、ゲストが長時間ベッティングを続けたくなるような仕組みを作り出しているのです。
カジノビジネスの利益は莫大です。そしてその利益は、このような狡猾な戦略によって生み出されているのです。次回カジノへギャンブルに行くときは、BGMとして流れる音楽にも注目してみてくださいね!